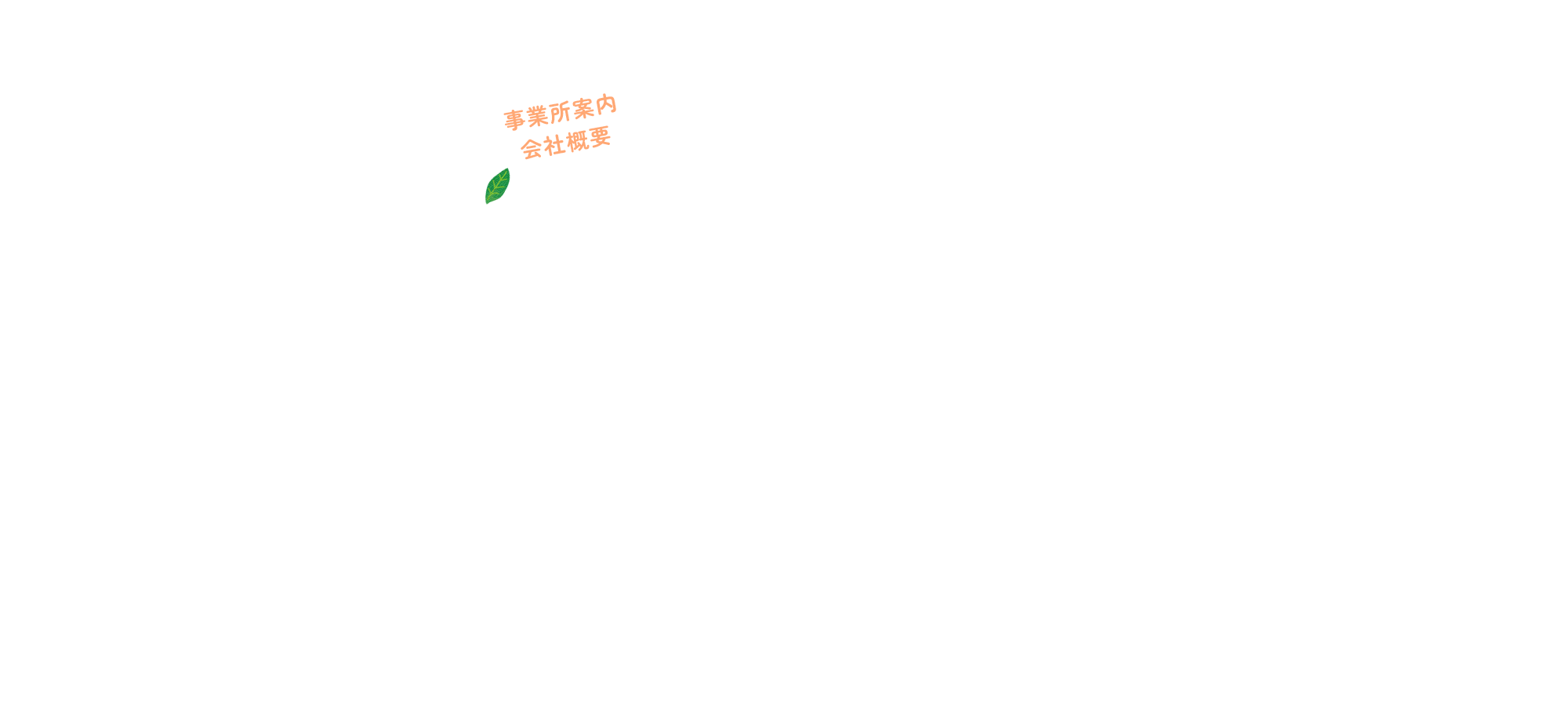ご挨拶
この度はCOCOROケアサービス、合同会社One Heartのホームページをご覧いただきありがとうございます。
当社では利用者さまにサービスを提供する際このように考えるようスタッフに指導しております。
「自分のおじいちゃん・おばあちゃん、お父さん・お母さんがどのような介護を受けたいのか」「自分が介護を受けるなら、どんな風にしてほしいか」
自分の家族・自分のことのように考えると、自然と良い介護・支援ができると考えているからです。
“One Heart” スタッフ一同心をひとつにし、津山市にお住まいのみなさまへ 安心して快適なサービスを提供できるよう精進いたします。
.
ご縁があり出逢ったご利用者さま、そしてこれから出逢うご利用者さまが住みよいご自宅で一日でも長く、変わらない自分らしい生活が過ごせるよう みなさまの暮らしをサポートいたします。
今後もCOCOROケアサービスを、よろしくお願いいたします。
代表 池口 由佳
COCOROケアサービス(津山市)
| 所在地 | 〒 708-0884 岡山県津山市津山口173-1 |
| TEL | 0868-32-8939 |
| FAX | 0868-32-8936 |
| 定休日 | 年末年始(12月30日から1月3日まで) |
| 時 間 | 事業所営業時間【月曜日~日曜日】8:30~17:30 サービス提供時間:8:00~19:00 |
| 提供地域 | 津山市(旧加茂町及び旧阿波村を除く)、奈義町、旧中央町、旧鏡野町の区域 |
会社概要
| 運営会社 | 合同会社One Heart |
| 事業所 | <津山事業所>COCOROケアサービス(事業所番号:3370302394) |
| 代表者 | 代表社員 池口 由佳 |
| 所在地 | 〒708-0884 岡山県津山市津山口173-1 |
| TEL | 0868-32-8939 |
| FAX | 0868-32-8936 |
| 設 立 | 平成30年10月1日 |
| 資本金 | 300万円 |
介護職員等特定処遇改善加算に基づく取り組みについて
介護職員等特定処遇改善加算とは
特定処遇改善加算とは、介護人材活用のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進めることを目的とした制度で2019年10月1日に創設されました。
COCOROケアサービスでは賃金改善以外の具体的な取り組みを、
下記のとおり行っています。
◆入職促進に向けた取り組み
他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者、有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築
◆資質の向上やキャリアアップに向けた支援
働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等
◆両立支援・多様な働き方の推進
有給休暇が取得しやすい環境の整備
◆腰痛を含む心身の健康管理
短時間労働者等も含む受診可能な健康診断・ストレスチェックや、健康管理対策の実施
◆生産性向上のための業務改善の取組
業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減
◆やりがい・働きがいの醸成
ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
感染症の予防およびまん延の防止のための指針
当事業所は利用者の健康と安全を確保するために、福祉サービスの提供者として、感染症の予防に努め、もし感染が発生した場合でも感染の拡大を防ぐため迅速な対応体制を整えるとともに、利用者の健康と安全を持続的に保護するために、本指針を定める。
- 感染症の予防及びまん延防止のための基本的な考え方
事業所においては、感染症に対する抵抗力が低い高齢者が障がい者が利用することで感染が広がりやすく、症状が悪化しやすい傾向があるため、利用者その家族、及び職員の安全を確保するための対策を講じ、適切な体制を整備する。
- 感染症の予防及びまん延防止のための体制
- 感染対策委員会の設置
- 設置の目的
事業所内での感染症を未然に防止するとともに発生時の対策を検討する
- 感染対策委員会の構成メンバー
管理者、サービス提供責任者
- 感染対策委員会の開催
おおむね6ヶ月に1回以上定期的に開催するとともに、感染症が流行している時期は必要に応じて随時開催する。
- 感染対策委員会の役割
- 事業所内感染対策の立案
- 感染症発生時の対応の検討
- 情報収集、整理、全職員への周知
- 行動マニュアル(BCP)等の作成
- 事業所内感染対策に関する職員への研修・訓練の実施
- 平時の対策
利用者や職員を感染から守るための基本的な予防方法である標準予防策(スタンダードプレコーション)を徹底する。標準予防策とは、血液や体液、分泌物、排泄物、傷のある皮膚や粘膜など、感染微生物が含まれている可能性があるという原則に基づいて行われる、感染拡大のリスクを軽減するための標準的な予防策である。
【標準予防対策の主な内容】
- 手指消毒(手洗い、手指消毒)
- 個人防護具(手袋、マスク、ガウン、ゴーグル、フェースシールドなど)の使用
- 呼吸器衛生(咳エチケット)
- 環境整備(整理整頓、清掃、感染性廃棄物の処理)
- 発生時の対応
- 事業所内で感染症が発生した場合は、発生状況を正しく把握し、必要に応じて医療機関や保健所、関係機関への連絡を行うとともに、消毒や感染経路の遮断に努める。事業所はその内容及び対応について全職員に周知する。
- 感染症またはそれが疑われる状況が発生した際には、利用者の状態や実施した措置などを記録する。
- 感染拡大の防止について、行政・保健所からの指示に従い、協議する。
- サービス事業所や関連機関と情報を共有し、連携して感染の広がりを抑制する。また、情報を外部に提供する際や事業所として公表する際には、個人情報の取り扱いに十分な注意を払う。
- 感染症対策マニュアル等の整備と活用
- 各事業所において、感染症対策マニュアルを整備するとともに、マニュアルに沿った感染対策に努める
- マニュアルを定期的に見直し、最新情報を掲載する。
- 「介護現場における感染対策の手引き(厚生労働省)」を踏まえ、感染対策に常に努める。
- 本指針の閲覧に関する基本方針
本指針は、利用者・家族や関係機関により希望があった場合はすぐに閲覧できるようにしておくとともに、ホームページで公表する。
附則
本指針は、令和6年 4月 1日から施行する。
虐待防止のための指針
1 高齢者虐待の防止に関する基本的考え方
虐待は高齢者の尊厳の保持や、高齢者の人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性が極めて高く、虐待の防止のために必要な措置を講じなければならない。
本事業所では、利用者への虐待は、人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、高齢者虐待防止法に基づき、高齢者虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するため、本指針を策定し、全ての職員は本指針に従い、業務にあたることとする。
2 虐待の定義
(1)身体的虐待
暴力的行為等で利用者の身体に外傷や痛みを与える又はそのおそれのある行為を加えること。また、正当な理由なく身体を拘束すること。
(2)介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)
意図的であるか、結果的であるかを問わず、行うべきサービスの提供を放棄又は放任し、利用者の生活環境や身体・精神状態を悪化させること。
(3)心理的虐待
脅しや侮辱等の言葉や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって利用者に精神的、情緒的な苦痛を与えること。
(4)性的虐待
利用者にわいせつな行為をすること。又は利用者にわいせつな行為をさせること。
(5)経済的虐待
利用者の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること。
3 高齢者虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項
当事業所では、虐待及び虐待と疑われる事案(以下「虐待等」という。)の発生の防止等に取り組むにあたって「高齢者虐待防止検討委員会」を設置するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施するための担当者を定めることとする。
(1)設置の目的
虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための対策を検討するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施する。
(2)高齢者虐待防止検討委員会の構成委員
・委員長は管理者が務める。
・委員会の委員は、管理者、サービス提供責任者とする。
(3)高齢者虐待防止検討委員会の開催
・委員会は、委員長の招集により年1回以上開催する。
・虐待事案発生時等、必要な際は、随時委員会を開催する。
(4)高齢者虐待防止検討委員会の審議事項
① 虐待に対する基本理念、行動規範等及び職員への周知に関すること
② 虐待防止のための指針、マニュアル等の整備に関すること
③ 職員の人権意識を高めるための研修計画策定に関すること
④ 虐待予防、早期発見に向けた取組に関すること
⑤ 虐待が発生した場合の対応に関すること
⑥ 虐待の原因分析と再発防止策に関すること
(5)高齢者虐待防止の担当者の選任
高齢者虐待防止の担当者は、坂手 温子とする。
4 高齢者虐待の防止のための職員研修に関する基本方針
職員に対する権利擁護及び高齢者虐待防止のための研修は、基礎的内容等の適切な
知識を普及・啓発するものであるとともに、権利擁護及び虐待防止を徹底する内容とし、以下のとおり実施する。
(1)定期的な研修の実施(年1回以上)
(2)新任職員への研修の実施
(3)その他必要な教育・研修の実施
(4)実施した研修についての実施内容(研修資料)及び出席者の記録と保管
5 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
(1)虐待等が発生した場合は、速やかに市町に報告するとともに、その要因の速やかな
除去に努める。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員であった場合は、役職位等の如何を問わず、厳正に対処する。
(2)緊急性の高い事案の場合は、市町及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先する。
6 虐待等が発生した場合の相談・報告体制
(1)利用者、利用者家族、職員等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応する。相談窓口は、3(5)で定められた高齢者虐待防止担当者とする。なお、虐待者が担当者の場合は、他の上席者等に相談する。
(2)利用者の居宅において虐待等が発生した場合は、関係機関に報告し、速やかな解決につなげるよう努める。
(3)事業所内で虐待等が発生した場合は、高齢者虐待防止担当者に報告し、速やかな解決につなげるよう努める。
(4)事業所内における高齢者虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、職員は日頃から虐待の早期発見に努めるとともに、高齢者虐待防止検討委員会及び担当者は職員に対し早期発見に努めるよう促す。
(5)事業所内において虐待が疑われる事案が発生した場合は、速やかに高齢者虐待防止委員会を開催し、事実関係を確認するとともに、必要に応じて関係機関に通報する。
7 成年後見制度の利用支援
利用者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて、行政機関等の関係窓口、社会福祉協議会、身元引受人等と連携のうえ、成年後見制度の利用を支援する。
8 虐待等に係る苦情解決方法
(1)虐待等の苦情相談については、苦情受付担当者は受付内容を管理者に報告する。
(2)苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処する。
(3)対応の結果は相談者にも報告する。
9 利用者等に対する指針の閲覧
職員、利用者及びその家族をはじめ、外部の者に対しても、本指針をいつでも閲覧できるよう、事務室等に備え付ける。また、事業所ホームページにも公開する。
10 その他虐待防止の推進のために必要な事項
権利擁護及び高齢者虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努める。
附則
この指針は、令和6年 4月 1日より施行する。
訪問介護BCP・感染症編
目次
1 目的
2 基本方針
3 段階別の実践項目
(1)BCP発動基準および定義
(2)対応体制
ア 組織
イ 組織内の情報共有方法
(3)初動対応
ア 第一報
イ 感染疑い者等への対応
ウ 感染疑い者が陽性だった場合の対処
エ 消毒・清掃等の実施
オ 休業の検討
(4)初動以降の対応
4 感染拡大防止体制の確立
ア 保健所との連携
イ 濃厚接触者への対応
ウ 防護具、消毒液等の確保
エ 関係者との情報共有
オ 過重労働・メンタルヘルス対応
カ 情報発信
5 平時からの備え
(1)体制構築・整備
(2)感染症防止に向けた取組の実施
(3)備蓄品の確保等
(4)研修・訓練の実施
1 目的
本計画は、新型コロナウイルス等の感染症が発生した場合に、サービス提供を継続し、或いは一時中断しても可及的速やかに事業活動を復旧しご利用者にサービスを提供するために実施すべき事項を定め、平時から円滑にこれを遂行できるよう準備すべき事項を定めたものである。
2 基本方針
個々の職員は、状況に対応するに際し原則として以下の方針(優先順位)に従うこと。
① ご利用者の安全の確保
② 職員自身や自分の家族等、大切な人の安全の確保
③ サービスの継続、再開に向けた活動
3 段階別の実践項目
(1)BCP発動基準および定義
ア ご利用者または職員若しくはその関係者(現場に出入りする事業所運営法人の役員を含む。以下「職員ら」という)、若しくは職員らの同居の家族に、感染症法所定の5類相当以上の感染症の感染疑い者又は濃厚接触者(以下、総称して「感染疑い者等」という)が発生した際に発動する。
イ 「感染疑い者」とは、発熱や咳、頭痛、味覚異常、嘔吐・下痢、倦怠感など感染を疑わせる何らかの症状が表れた者、または感染者と濃厚接触した者をいう。
ウ 「濃厚接触者」とは、感染者の発症から2日前以降に当該感染者と接触のあった者で、マスクなどの感染予防策をせず、対面で互いに1メートル以内の距離で15分以上の接触をした場合をいう。
(2)対応体制
ア 組織
a 管理者など事業所の長に当たる者を感染対策本部長(以下「本部長」)とし、本部長の統括のもと感染症対策委員会(以下「委員会」)が中心となり対応を進める。
b本部長は事業所全体としての意思決定、事業所代表として外部との連携、現場への指示、情報の集約と分析、本部への報告等を行う。ただし事業所とは別に法人本部が存在する場合は、意思決定の方法は、緊急性が認められない限り原則として代表を中心とする本部の指示を仰ぐものとする。
c 本部長の補佐役として副部長を定める。副部長は本部長が指名する。
副部長は主に本部長の補佐、情報の集約と進捗管理、記録等を行う。
イ 組織内の情報共有方法
感染に関する情報は要配慮個人情報であるため、誤送信等のトラブルのないよう極力事業所内において対面にて職員間で共有すること。突発的なクラスター発生など、緊急やむを得ない場合は本部長の判断により職員らの連絡網を活用し全体共有する。
(3)初動対応
最初の感染疑い者等が発生した時点以降において、以下を並行して行う。
なお、以下は必ずしも全てにおいて履行しなければならないというものではなく、事案ごとに委員会において検討し、緊急性や深刻度、時勢の状況等に応じ柔軟かつ臨機応変に対応すること。
ア 第一報
・感染疑い者等が出た事実、当人の容態、感染前後の経緯等を本部長へ報告、事業所内で情報共有
・地域での身近な医療機関、受診・相談センターへ連絡
・指定権者、保健所への報告
イ 感染疑い者等への対応
(ご利用者が感染疑い者の場合)
・ご本人、ご家族、担当ケアマネージャーに連絡を取り、サービス提供の中止を決定
・医療機関受診の支援
(職員らが感染疑い者の場合)
・医療機関受診
・自宅待機指示(可能であればリモート勤務)
ウ 感染疑い者が陽性だった場合の対処
(ご利用者が陽性と判明するまでの期間)
・原則としてサービスは休止するが、サービスの必要性、感染リスク、職員の状況等に鑑み、例外的に実施する場合がある。
(ご利用者が陽性の場合)
・サービス利用は休止
・保健所、保険者へ報告
・医療機関受診の支援
(職員らが陽性の場合)
・速やかに医療機関へ入院させる。
・陽性の場合は出勤停止(欠勤扱い)。
※陰性の場合でも状況に鑑み自宅待機を指示する場合、6割相当以上の休業補償を支給。
・当該人と濃厚接触した者を確認する。濃厚接触した職員らは自宅待機とする。
エ 消毒・清掃等の実施
・保健所の指示に従い、感染疑い者等の利用した事務所やご利用者宅の消毒・清掃
・手袋を着用し、消毒用エタノールまたは次亜塩素酸ナトリウム液で清拭後、湿式清掃し乾燥させる。
オ 休業の検討
・保健所から休業要請があれば従う。都道府県、保健所等の意見を聴きつつ、感染者の人数、濃厚接触者の状況、勤務可能な職員の人数、消毒の状況等に応じて本部長が決定する。
感染疑い者が少数であり、陰性と判断されるまでの間は一時的に提供を休止する場合がある。
・職員全員が感染するなど実質的に稼働不能に陥った場合は、本部長がこれを見越し極力早期の段階で担当ケアマネや保険者に報告・相談し、担当ご利用者の引き継ぎを求める。
(休業した場合)
・ご利用者・ご家族への説明とホームページでの告知(業務停止日と業務再開見込、窓口を提示)
・各ご利用者の担当ケアマネージャーへの事業所交代の検討・打診
・再開基準→陽性者ないし濃厚接触者が出た場合、当該人が事業所を訪れた最終日から14日経過の期間において、感染疑い者が新たに出現しなかった場合に再開する。
(4)初動以降の対応
・休業しない場合は、稼働可能な職員らにおいて可能な限り担当ご利用者へのサービス提供を継続し、順次自宅待機職員の復帰を待つ。必要に応じて他事業所にご利用者の引き継ぎを依頼する。
・休業した場合は、上記再開基準を満たした場合、または本部長が再開可能と判断した場合に事業を再開する。
4 感染拡大防止体制の確立
ア 保健所との連携
・濃厚接触者の特定への協力
感染症の症状が出現する2日前以降の接触者リスト、直近2週間の勤務記録、ご利用者の介護記録(体温、症状等をできる限り詳細に記録したもの)、事業所内に出入りした者の記録等を取り保管する。
・ 感染疑い者等が発生した段階で、感染が疑われる者、(感染が疑われる者との)濃厚接触が疑われる者のリストを作成する。
・感染対策の指示を仰ぐ
イ 濃厚接触者への対応
・ご利用者→自宅待機、医療機関の受診、ケアマネとの調整
・職員→自宅待機、リモートワーク
ウ 防護具、消毒液等の確保
・在庫量・必要量の確認
個人防護具、消毒液等の在庫量・保管場所を確認する。
ご利用者の状況等から今後の個人防護具や消毒液等の必要量の見通しをたて、物品の確保を図る。
・調達先・調達方法の確認
事業所内で情報交換し、調達先・調達方法を検討する。
不足が見込まれるは自治体、地域の事業者団体に相談する。
エ 関係者との情報共有
・事業所/法人内での情報共有
時系列にまとめ、感染者の情報、感染者の症状、その時点で判明している濃厚接触者の人数や状況を報告共有する。
管轄内保健所や行政からの指示指導についても、関係者に共有する。
事業所内での感染拡大を考慮し、社内で各自最新の情報を共有できるように努める。
ご利用者や職員らの状況(感染者、濃厚接触者、勤務可能な職員数等)、休業の期間、休業中の対応、再開の目安等について、社内で共有する。
感染者や濃厚接触者となった職員らの兼務先を把握している場合は、個人情報に留意しつつ必要に応じて情報共有を行う。
・ご利用者やご家族との情報共有
休業の有無、休業の期間、休業中の対応、再開の目安等について、ご利用者・ご家族と情報共有を行う。
・自治体(指定権者・保健所)との情報共有
・関係業者等との情報共有
管轄内保健所や行政からの指示指導についても、関係者に共有する。
休業の有無、休業の期間、休業中の対応、再開の目安等について、指定権者、保健所、他の介護保険事業所、委託業者等と情報共有を行う。
必要に応じて、包括、相談支援事業所等と相談し、地域で当該利用者が利用等している医療機関や他サービス事業者への情報共有に努める。
オ 過重労働・メンタルヘルス対応
・労務管理
職ら員の感染状況等に応じて勤務可能な職員をリストアップし、調整する。
職員の不足が見込まれる場合は、早めに応援職員の要請も検討し、可能な限り長時間労働を予防する。
勤務可能な従業員の中で、休日や一部の従業員への業務過多のような、偏った勤務とならないように配慮を行う。
・長時間労働対応
連続し長時間労働を余儀なくされる場合、週1日は完全休みとする等、一定時間休めるようシフトを組む。
定期的に実際の勤務時間等を確認し、長時間労働とならないよう努める。
休憩時間や休憩場所の確保に配慮する。
・コミュニケーション
日頃の声かけやコミュニケーションを大切にし、心の不調者が出ないように努める。
風評被害等の情報を把握し、職員の心のケアに努める。
・相談窓口 →本部長
カ 情報発信
・関係機関・地域・マスコミ等への説明・公表・取材対応
↓
本部長が対応する。陽性者が発生した場合、事業を一時休業した場合は事実をホームページ上に公表する。取材は全て本部長が対応する。
公表内容については、利用者・家族・職員のプライバシーへの配慮が重要であることを踏まえた上で検討する。
利用者・家族・職員が、報道を見て初めてその事実を知ることがないよう留意する。発信すべき情報については 遅滞なく発信し、真摯に対応する。
5 平時からの備え
(1)体制構築・整備
本部長が意思決定を行い、全ての事項につき担当者となる。本部長は随時担当を他職員に委託できる。
(2)感染症防止に向けた取組の実施
必要な情報収集と感染防止に向けた取組の実施
新型コロナウイルスをはじめとする感染症に関する最新情報(感染状況、政府や自治体の動向等)の収集
基本的な感染症対策の徹底
ご利用者や職員らの日頃の体調管理
事業所内出入り者の記録管理
組織変更・人事異動・連絡先変更等の反映
(3)備蓄品の確保等
別紙備蓄品リストを年1回本部長と副部長がチェックし、不足分を補充する。
(4)研修・訓練の実施
定期的に以下の研修・訓練等を実施し、BCPを見直す。
BCPを関係者で共有
BCPの内容に関する研修
BCPの内容に沿った訓練(シミュレーション)
本BCPは、原則として毎年4月に更新する。
以上
訪問介護BCP・災害編
目次
1 目的
2 基本方針
3 緊急時の対応
- BCP発動基準
- 対応体制
ア 組織
イ 施設本部の設置場所
ウ 組織内の情報共有方法
- 初動
ア 事業所に居る職員
イ―1 事業所に居ない職員(サービス中)
イ―2 事業所に居ない職員(非番)
ウ 職員の参集後
- 復旧段階
ア 業務
イ ライフライン停止期間中の対応
ウ 事業再開
4 平常時の対応
- 建物・設備の安全対策
- 電気・水道等のライフラインが停止した場合の対策、必要品の備蓄等
- 避難と安否確認
- 研修・訓練の実施
5 他施設及び地域との連携
1 目的
本計画は、大地震等の自然災害が発生した場合に、サービス提供を継続し、或いは一時中断しても可及的速やかに事業活動を復旧しご利用者にサービスを提供するために実施すべき事項を定め、平時から円滑にこれを遂行できるよう準備すべき事項を定めたものである。
2 基本方針
下記のうち一つを選ばなければならない状況では、以下の優先順位で対応すること。
① 職員自身や自分の家族等、大切な人の身の安全の確保
② ご利用者の身の安全の確保
③ サービスの継続、再開に向けた活動
3 緊急時の対応
以下、「地域一帯で震度5強以上の地震が日中のサービス提供時間に発生。電気、ガス、水道のライフラインは4~7日で復旧する見込み」との想定で計画を定める。
(1)BCP発動基準
市内で震度5強以上の地震が発生した場合、発災直後から自動的に発動。
その他、災害対策本部長が必要と判断した場合、原則としてラインアプリのBCP専用グループ内で通知を行い、これを覚知した者から順次発動とする。
(2)対応体制
ア 組織
a 管理者など事業所の長に当たる者を災害対策本部長(以下「本部長」)とし、本部長の統括のもと災害対策本部(以下「本部」)が中心となり対応を進める。
b本部長は事業所組織における意思決定、事業所代表として外部との連携、現場への指示、情報の集約と分析、法人本部への報告等を行う。意思決定の方法は原則として本部長が単独で行うが、可能であれば例外的に理事長を中心とする法人本部の指示を仰ぐものとする。
c 本部長の補佐役として副部長を定める(本部長が指名する)。
副部長は主に本部長の補佐、情報の集約と進捗管理、外部との連携等を行う。
d 各役割担当
・情報管理係 ご利用者や職員等関係者の情報を定期的にアップデート、管理、発信
する責任者
・行政との連絡係 行政からの通達、指示を取りまとめ全員に伝達し、
行政への要望をする窓口となる。
・記録係 被災状況、被害、日々の職員の働き等の重要な情報を日々記録する。
イ 本部の設置場所
本部長の判断により、以下の優先候補順に設置する。
第一候補 事業所内会議室
第二候補 事業所内の広い共有スペース
第三候補 事業所外の広範かつ安全なスペース
ウ 組織内の情報共有方法
ラインアプリのBCP専用グループを設置し、情報共有は原則としてこれによるものとする。ラインを使えない者についてはメール、電話、災害用伝言web等で補完する。
(3)初動
BCPの発動直後から、各職員が以下を並行して行う。
ア 事業所に居る職員
・自分自身、および関係者の安全確保・確認
・自身の身の安全の確保
揺れが収まるまで頭を保護し待機 ヘルメット等の確保
・避難経路の確認と確保
・避難計画に沿って行動し避難する。ガラス片等で受傷しないよう注意。
以後は、可能な限りウ所定の行動を行う。ただし自身の家族等に
ついて必要な場合は、その安否確認等を優先する。
イ―1 事業所に居ない職員(サービス中)
・自分自身、およびご利用者の安全確保・確認
・各自、本部に自身とご利用者の安否の状況報告をする。
・動ける者はご利用者の安全を確保した後、近隣住民の人命救助または事業所へ参集。他のご利用者の対応業務と復旧作業にあたる。
イ―2 事業所に居ない職員(非番)
・自分自身、および関係者の安全確保・確認、参集
・各自、家族の安全確保等必要な対応が完了し次第、本部に安否の状況報告をする。
・動ける者は各々事業所へ参集、ご利用者の対応業務と復旧作業にあたる。
ウ 職員の参集後
・本部が全員の状況確認。全員無事の場合、次の段階に移る。
・音信不通、受傷、行方不明など安全が危ぶまれる者がいる場合、できる限り全員で
連携し安全確保に務める。但し自らを犠牲にしてはならない。
・担当ご利用者の安否確認や救助を、下記順番に基づき可能な範囲で行う。
a優先度1 災害発生時、自宅に居ると思われる利用者に対して
被災環境、要介護度、家族構成、認知症の有無等を考慮し、最も優先度の高いと思われる利用者から安否確認、救援計画を発動する。ケアマネに状況確認後、必要に応じ救命用具等を持ち現場に向かう。
・到着後自宅にいることが危険な場合、随時避難場所まで誘導し、ご家族に連絡。
b優先度2 災害発生時、デイやショート等に居る、あるいは訪問介護利用中と思わ れるご利用者に対して
事業所に電話をかけ安否確認。対応は原則として現場の事業所に任せる。
c優先度3 通話や移動が制限される場合、最寄りの避難所等を訪問し行政の指導に従い救助活動等を行う。
※ サービス提供中に被災した利用者については、担当職員が適宜救命と安全措置を講じること。
(4)復旧段階
ア 業務
被災翌日から、対応可能な職員は事業所に出勤し、本部を中心に以下を行う。
・ご利用者の状況確認と必要な物資、サービスの提供
・各ご利用者の介護計画その他のデータを復旧・確認する。データがない場合は順次優先度の高いご利用者ごとにカンファレンスを実施しメモ帳等に記録する
・行政からの指示、見解の取りまとめと共有
・各事業所と情報共有、事業再開に向けた協議
・事業所内の危険物の除去、清掃等
・ホームページやSNSでの情報発信(関係者、地域、マスコミ等への状況報告や応援要請等)
イ ライフライン停止期間中の対応
上水:飲料、生活用水(調理、洗体、洗面等)の確保と節約、消費量のコントロール
下水:生活用水を排泄や洗濯の用水に回す。
電気:自家発電機や電池で代替する。
ガス:カセットコンロとガスボンベで代替。
通信:災害用伝言ダイヤル、無線機を利用。
ウ 事業再開
事業再開の目処が立ち次第、ご利用者ご家族、各事業所に連絡し、順次再開する。
4 平常時の対応
(1)建物・設備の安全対策
・データの保存とバックアップ(クラウドの活用等)
・パソコン類の転倒転落対策
・建物の耐震状況の確認
・ヘルメット、AED、応急手当キット、バール等救出道具の確保
・玄関当のドアやエレベーターが衝撃により閉鎖したときの対策
・キャビネットや家具設備の転倒予防策
・消火器、スプリンクラー、通報システムの動作確認
(2)電気・水道等のライフラインが停止した場合の対策、必要品の備蓄等
電気 発電機、電池の備え
水道 ペットボトル1.5リットル5本分(3年で更新)、簡易ろ過装置
ガス カセットコンロやガスボンベの備蓄
通信 伝言ダイヤルの活用法の確認、パソコンが破損した場合に備えデータをバックアップ。
必要品の備蓄 医薬品・衛生用品・日用品など(別紙リスト参照)
移動(車) ガソリンを常に満タンにしておくよう配慮する。バッテリーの消耗具合の確認とメンテナンス。
(3)避難と安否確認
・年間計画に基づく避難訓練の実施
・災害マップを事業所内に掲示。ご利用者宅に配布し避難場所を案内する
・独居、自力で避難できないご利用者のリストアップ(担当ケアマネと個別協議)
・避難場所となる施設や学校との合同訓練、打ち合わせの実施
・職員・ご利用者の安否に関する情報共有
連絡先を常に最新・正確なものにしておく(情報のアップデート)。
契約時やモニタリング、サー担時等に「災害時にどうするか」を話し合っておく。
(4)研修・訓練の実施
・備品の棚卸しと更新(6月)
・一次救命、応急処置法の習得(9月)
・災害想定で安否確認をリハーサル 伝言ダイヤルを使ってみる(11月)
5 他施設及び地域との連携
・避難場所となる施設や居宅、デイ、ショート等と合同研修
・自治体の研修に参加し、地元行政の考え方や進捗を把握する。
・民生委員、包括との連携
本BCPは、原則として毎年4月に更新する。
ハラスメント防止のための指針
当事業所は、利用者に対して安定した居宅介護支援サービスを提供するため、
職場及び訪問先・利用者宅におけるハラスメント防止のための本指針を定める。
1 ハラスメント防止に関する基本的考え方
本指針におけるハラスメントとは、下記を言う。
(1)職場におけるハラスメント
ア パワーハラスメント
3つの要素すべて満たした場合、職場におけるパワハラに該当するものとする。
- 優越的な関係を背景とした言動であって
- 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより
- 労働者の就業環境が害されるもの
<具体的な例>
- 身体的な攻撃(暴行・傷害)
・殴打、足蹴りを行うこと
・相手に物を投げつけること
- 精神的な攻撃(脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言)
・人格を否定するような言動を行うこと。相手の性的指向・性自認に関する侮辱的な
言動を行うことを含む
・業務の遂行に関する必要以上に長時間にわたる厳しい叱責を繰り返し行うこと
・他の労働者の面前における大声での威圧的な叱責を繰り返し行うこと
・相手の能力を否定し、罵倒するような内容の電子メール等を当該相手を含む複数
の労働者宛てに送信すること
- 個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)
・労働者を職場外でも継続的に監視したり、私物の写真撮影をしたりすること
・労働者の性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報について、当該労働者の了解を得ずに他の労働者に暴露すること
イ セクシュアルハラスメント
- 対価型セクシュアルハラスメント
セクハラ行為を受けた労働者が、その言動に対して拒否、抗議などの対応をしたことで、事業主等から解雇、降格、減給等の不利益を受けること
- 環境型セクシュアルハラスメント
職場で行わるセクハラ行為によって仕事の環境が損なわれ、仕事をする上で見過ごせないほど重大な支障が生じること
➂ 同性に対するものも含まれる
同性から同性に対するもの、女性から男性に対するものもセクハラに該当する
<具体的な例>
- 性的及び身体上の事柄に関する不必要な質問・発言
- わいせつ図画の閲覧、配布、掲示
- うわさの流布
- 不必要な身体への接触
- 性的な言動により、他の従業員の就業意欲を低下せしめ、能力の発揮を阻害する行為
- 交際・性的関係の強要
- 性的な言動への抗議又は拒否等を行った従業員に対して、解雇、不当な人事考課、配置転換等の不利益を与える行為
- その他、相手方及び他の従業員に不快感を与える性的な言動
(2)訪問先・利用者宅でのハラスメント
ア パワーハラスメント
- 身体的暴力を行うこと
- 違法行為を強要すること
➂ 人格を著しく傷つける発言を繰り返し行うこと
<具体的な例>
- 強くこづいたり、身体的暴力をふるう
- 攻撃的態度で大声を出す
- 机や椅子などをたたいたり蹴ったりする
- 書類を破る
- 制度上認められていないサービスを強要する
- サービス提供上(契約上)受けていないサービスを要求する
- あるいは「他のスタッフはやってくれた」など他者を引き合いに出して強要する
- 「バカ」「クズ」などと言う
- 人格を否定するような発言をする
- 「ハゲ」「デブ」「ネクラ」など身体や性格の特徴をなじる
- からかいや皮肉を言う
- 差別的な発言をする
イ セクシュアルハラスメント
- 利益・不利益を条件にした性的接触または要求をすること
- 性的言動により、サービス提供者に不快な念を抱かせる環境を醸成すること
<具体的な例>
- 食事やデートへの執拗な誘い
- 性的な関係を要求する
- 会社や管理者へのクレームなどをちらつかせて誘いをかける
- サービス提供上不必要に個人的な接触をはかる(体に触れてくる)
- 繰り返し性的な電話をかけたり、他者に対して吹聴する
- サービス提供中に胸や腰などをじっと見る
- 性的冗談を繰り返したり、しつこく言う
- 握手した手を離さない
- 匂いを嗅ぐ
- 体をぴったりくっつける
- アダルトビデオを流す
- わいせつな本を見えるように置く
2 ハラスメント対策
(1)従業員
本指針に基づいたハラスメント防止を徹底する定期的な研修(年1回以上)を実施する。
(2)利用者・家族
居宅介護支援事業契約時等ハラスメントについて説明する。
3 ハラスメントに関する相談窓口と対応
- 事業所におけるハラスメントに関する相談窓口担当者は次の者を置く。
相談窓口担当:COCOROケアサービス 管理者 池口 由佳
電話 0868-32-8939
相談窓口担当者は、公平に相談者だけなく行為者についてもプライバシーを守り対応する。電話、メール、ラインでも相談を受け付ける。
(2)労働者は、利用者・家族からハラスメントを受けた場合、相談窓口担当者に報告・相談する。相談窓口担当者は、必要な対応を行う。
(3)相談窓口担当者は、被害者への配慮のための取組(メンタルヘルス不調への相談対応、行為者に対して1人で対応させない等)を行う。
(4)相談窓口担当者は、相談や報告のあった事例について問題点を整理し、被害防止のため、マニュアル作成や研修実施、状況に応じた取組を行う。
4 利用者等に対する当該指針の閲覧
本指針は利用者・家族や関係機関が閲覧できるようホームページへ掲示する。
5 その他ハラスメント防止のために必要な事項
当事業所のハラスメント防止マニュアルについては、「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル」「(管理職・職員向け)研修のための手引き」に基づいて対応する。
附則
本指針は、令和6年 4月 1日より施行する。